
渋滞で横をサッと抜けていく二輪。――**「バイク すり抜け なぜ禁止しない?」**と感じたことはありませんか。結論から言うと、日本では“全面禁止の明文規定はない一方で”、状況次第で違反になり得るグレーゾーンです。本記事「バイクのすり抜け なぜ禁止しない?法的根拠と安全策を検証」では、道路交通法の条文と実務運用を押さえつつ、どこがアウトで、どこまでがセーフなのかを具体例で整理します。
読了メリットは3つ。
- 法律の枠組み(追越し・進路変更・安全運転義務)を“条文ベース”で理解できる
- 取締り・過失割合の落とし穴を事例で把握し、ムダなリスクを避けられる
- 今日から使える実践的な安全策(差速の目安・合図・装備・チェックリスト)が手に入る
さらに、英国・米カリフォルニアなどの海外事例も対比し、「なぜ日本は全面禁止にしないのか」という政策的背景にも触れます。二輪ライダーはもちろん、四輪ドライバーにとっても“驚かされない・驚かせない”ための実務ガイド。感情論ではなく、データと法律で納得できる答えを一緒に見つけていきましょう。
よく読まれている記事
結論|バイクのすり抜けは「全面禁止ではない」—道路交通法の枠内で条件次第
すり抜けは、日本の道路交通法に**「一律で全面禁止する」明文はありません**。その一方で、状況によっては「追越し」「進路変更」「安全運転義務」などの規定に触れて違反になるケースがある——この二つがセットで理解の要点です。
結論としては、“いつでもOK”ではないが“常に違法”でもない。渋滞時の車列間通過や停止車列の横通過など、具体的な場面ごとに“条件”を満たせるかが判断基準になります。
先に3行要約|「明確な全面禁止規定なし」「安全運転義務が最上位」「違反は状況で変わる」
- 全面禁止の条文はない:ただし“どこを・どう通るか”で別規定に抵触し得る
- 安全運転義務が最上位:視認性・速度差・路面・周囲予測など“危険回避”が基準
- 状況で違反が変わる:センターライン越え、路肩走行、交差点直前の割込み等はアウトになりやすい
本記事の対象読者|渋滞路での実務判断・法的根拠・安全策を知りたい二輪/四輪ユーザー
- 二輪ライダー:渋滞や右折待ちで“どこまでが許容されるのか”を実務レベルで知りたい方
- 四輪ドライバー:すり抜けに驚かないための確認動作・合図の受け止め方を知りたい方
- 双方の安全担保:事故・接触時の**落とし穴(過失割合、ドラレコの使い方)**まで整理したい方
ポイント:本記事は「条文→運用→具体場面→実践」の順で、合法/違法の境目と現場での守り方をわかりやすく解説します。海外(英国・米カリフォルニア等)の運用も対比し、「なぜ日本は全面禁止にしていないのか」という政策的背景も俯瞰します。
法的整理|「なぜ禁止しない?」を条文で確認
「すり抜け」は、法律上“単独の禁止条文”があるわけではありません。代わりに、複数の一般規定(追越し・進路変更・通行方法・安全運転義務など)に照らして、OKにもNGにもなり得る——これがグレーと言われる理由です。ここでは、現場判断の軸になる考え方を“条文の役割ごと”に整理します。
道路交通法のキモ|第28条(追越し)・第26条の2(進路変更)・第70条(安全運転義務)
- 追越しの考え方(第28条)
車列の“間”を通る動作が、結果として前車を先に出るなら「追越し」に該当し得ます。- 追越し中は側方間隔の確保が大前提。ミラー接触や幅寄せを誘発するような通過はアウト。
- 交差点やその手前、横断歩道付近など追越し禁止の場面にかかると、一気に違反リスクが高まります。
- 進路変更(第26条の2)
すり抜けの最中にレーンをまたぐ・車列の間へ斜め進入する行為は、進路変更に該当。- 合図(ウインカー)と安全確認の徹底が必要。急な割込みやブレーキを強いる挙動は違反の典型。
- 「前の車の側方へ寄る→さらに前へ出る」といった連続した変位も、進路変更として評価されます。
- 安全運転義務(第70条)
もっとも幅広く適用される“安全の総合条項”。- 速度差が大きい/視認性が悪い(夜雨・大型車の死角)/路面が荒れている——こうした条件での無理な通過は、この条項で違反認定されやすいです。
- 逆に言えば、差速を抑え、見える・止まれる状態を保つことが、合法性と安全性の両方に効いてきます。
「車両通行帯」とすり抜けの関係|第20条・第18条の読み解き方
- 車両通行帯(複数レーン)のある道路(第20条)
それぞれの車両は通行帯(レーン)を選択して通行します。車線間を通過する“レーン間走行”は、状況によっては通行帯に属さない走行と解され、進路変更・追越し・安全運転義務の三点セットで見られがち。- 実務上は、停止車列の間を低速・差速小さく通るか、同一レーン内での超徐行にとどめるほど、違反認定リスクは下がります。
- 車両通行帯のない道路/左側端通行(第18条)
普通自動車等は左側端寄りが原則。二輪が“左端の余地”を安全に活用する余地はありますが、路肩(路外)や白線外に逃げるのはNGになりやすいポイント。- 路肩は通行部分ではない扱いになるため、左側からの無理な追越しや路肩走行は違反の典型です。
禁止になり得るケース|センターライン越え・対向車線走行・路肩走行・交差点進入時
- センターライン越え/対向車線走行
前車を抜くために反対車線へはみ出すのは、追越し違反+危険運転の評価に直結。見通しの悪いカーブ・交差点手前は特に危険です。 - 路肩走行(左側白線外)
路肩は走行のための部分ではないので、通行区分違反等が問われやすい。側溝や砂利、開き扉・歩行者など即事故要因も多いです。 - 交差点・横断歩道・踏切付近
これらは追越しや進路変更に強い制約がかかる場所。停止車列の先頭付近へノー合図で割り込む、歩行者の横を差速大きく通過する行為はNGの代表例。 - 大型車脇のすり抜け
ミラーの高さ・内輪差・死角が重なるため、安全運転義務違反になりやすい領域。とくに左折巻き込みや右折時の張出しに注意が必要です。
まとめ:法律は「すり抜け」という言葉で直接規制していません。その代わり、通行方法(通行帯/左側端)・進路変更・追越し・安全運転義務の複合評価で判断されます。差速・位置取り・合図・視認性を丁寧に整えるほど、リスクも違反可能性も下げられます。
行政・実務の見解を俯瞰|取締り運用とグレーゾーンの実態
「すり抜け」単体での一律取締りというより、別の条項(進路変更・追越し・通行区分・安全運転義務)で“結果的に”指摘されるのが実務です。現場は“危険の具体性”を重視します。つまり、差速・位置取り・合図・周囲の予測可能性が評価の中心です。
取締りが発生しやすい典型例|すり抜け中の進路変更違反・安全運転義務違反ほか
- 停止車列の先頭直前でノー合図割込み
→ 合図不履行+進路変更違反にされやすい。歩行者・自転車・右左折車の動きが重なる地点は特にリスク大。 - 大型車の左側すり抜け中に巻き込みリスク
→ 左折や内輪差の予見可能性が高く、安全運転義務の観点で厳しめ評価。雨夜・渋滞末尾はさらに要注意。 - レーン間を“差速大”で通過
→ 速度差が20〜30km/h以上になると、回避余地が乏しい危険運転として見られがち。 - 路肩・白線外の走行
→ そもそも通行区分違反の典型。ドア開放・歩行者・段差など“即事故要因”が多い領域。
反則金/違反点数の目安|適用条項ごとのリスクと実務での落とし穴
- 実務の傾向:いわゆる軽微違反であっても反則金は数千円台〜、点数は1〜2点が中心。
ただし、複合違反(例:合図不履行+進路変更)や接触・転倒を伴う事故が絡むと、処分は一段階重くなります。 - 落とし穴:
- “徐行中だから大丈夫”は誤解。進路変更の合図・安全確認は速度に関係なく必須。
- “車両通行帯の間”にいる時間が長いほど、通行方法違反や安全運転義務の評価材料が増える。
- スマホ・ドラレコの映像は双方に有利にも不利にもなる。“見える・止まれる”態勢を映像で示せると局面が変わります。
判例・交通事故紛争の論点整理|「追越し」認定と過失割合に影響する要素
- “追越し”認定の分かれ目:
同一レーン内の通過か、レーンを跨いだのか/前車の直前で進路変更したか/交差点・横断歩道に近接していたか——これらが法的評価に直結。 - 過失割合を左右するポイント:
- 差速(15〜20km/hを超えると不利になりやすい)
- 合図・視認性(ウインカー、ブレーキランプ、反射材、ハイビジ)
- 位置取り(大型車の死角、右左折車の軌跡内)
- 環境条件(夜間・雨天・渋滞先頭の信号変化・見通し)
- 記録(ドラレコ・GPSログ・目撃証言)
- 実務的アドバイス:紛争に備えるなら、「差速を抑える」「手前で明確に合図」「死角に長居しない」の3点が最も効果的。記録装備は**前後2カメ(ナンバー読取・夜間強いもの)**が心強いです。
要するに、“危険の具体性”が高い場面ほど、同じ挙動でも違反・過失評価が上がるということ。差速・合図・位置取り・視認性の4点を整えることが、取締りと事故の二重リスクを同時に下げます。
海外比較で理解を深める|“全面禁止しない”の政策的背景
すり抜け(英:Filtering/Lane Splitting)は、渋滞緩和・二輪の機動性・占有幅の小ささといった交通効率の向上を理由に、海外では「条件付きで容認」される例が少なくありません。共通するポイントは、
- 速度差(差速)を小さく保つ
- 視認性を高め、予測可能な挙動を取る
- 禁止エリア(交差点直前・バスレーン等)を明確化
の3点。以下、主要国・地域の“考え方”と実務的な目安をまとめます。
英国:Highway Code(Rule 88 等)—Filteringは“慎重に行えば容認”
- 位置づけ:二輪のFiltering(低速車列の側方通過)は慎重に行えば許容というスタンス。
- 実務の要点:
- 差速は控えめ(おおむね15〜20km/h以下を目安にすると安全余裕が広がる)
- ドア開き・右左折・歩行者の飛び出しを強く警戒
- ハイビジ装備・ヘッドライトONで“見える化”
- 禁止・注意領域:交差点・横断歩道付近、見通しの悪いカーブ、大型車脇の長居は回避。
米カリフォルニア:Lane Splitting 容認—“安全第一、差速は控えめ”
- 位置づけ:Lane Splittingは州として容認。ただし「安全を最優先」「状況に応じた速度選択」が前提。
- 実務の要点:
- 渋滞時の低速車列間で、差速を抑えるほどリスクが下がる
- 車線中央〜車線間を短時間で通過し、死角に滞在しない
- ミラー高さ・車線幅が狭い区間では見送り判断も
- 禁止・注意領域:高速での差速拡大、交差点手前の割込み、路肩走行はNG。
フランス/豪州:条件付き容認(区域・速度・差速の明文化)
- フランス:都市圏を中心に区域・条件を限定した運用(実験・ガイドライン)が行われ、速度上限・差速に明確な基準を設けるケースがある。
- オーストラリア(州法ベース):NSW、VIC、QLD、ACTなどでは、低速域(例:30km/h以下)でのFilteringが条件付きで容認される運用。
- 実務の要点(共通):
- 明確な速度上限(例:30km/h)や差速の上限を設け、交差点直前やバスレーンなどの禁止区間を設定
- 取り締まり・事故分析を踏まえ、安全基準を継続的に更新
海外から学べる実装ポイント(日本での安全行動に転用可)
- 差速は常に控えめ:15〜20km/h以下を基本線とし、混合交通・見通し不良ではさらに下げる
- 予測可能な挙動:早めの合図・一定のライン・短時間通過で“読める動き”を徹底
- “見える化”装備:ハイビジ上下・反射材・デイライト/ポジション、前後ドラレコで抑止&証拠
- やらない勇気:大型車の死角・交差点手前・路肩代用は見送り判断が最適解になることも
まとめ:海外の共通解は、「速度差を小さく」「見える・読める」「禁止区間は明確」。結果として、“全面禁止ではない”が“無制限でもない”というバランス設計です。日本でも同じ原理で安全性は大きく高められます。
安全策の結論|「差速を抑える」「予測運転」「見せる装備」が命綱
“禁止ではない=いつでもOK”ではありません。安全に配慮したすり抜けの核心は、差速を小さく保つ・先を読む・自分を見せるの3点です。ここを外すと、合法性の評価も安全も一気に崩れます。
速度差15–20km/h以下を目安に|前後ドラレコ・ハイビジで“見える化”
- 差速の基準:周囲の車両速度に対して**+15〜20km/h以内**を上限の目安に。
- 例)周囲0〜10km/hの渋滞なら10〜25km/h程度の超徐行。
- 見通し不良(夜間・雨・大型車脇)はさらに-5〜10km/h。
- ライン取り:レーン間を長居しない・一定のトレースで“短時間通過”。蛇行やフラつきはNG。
- 視認性の底上げ:
- ハイビジ(高視認)ウェア/反射材/ヘルメット上部リフレクターで他車の“視界に残す”。
- デイライト/ポジションランプ常時点灯で昼間の被視認性UP。
- 前後ドラレコは抑止+事後の証拠。夜間・逆光に強いモデルを選択。
すり抜け前のチェックリスト|ブラインドゾーン・路面・ウインカー/ドア開き予兆
- 死角の確認:大型車の左前/右後ろは“消える領域”。ミラー越しに運転者の顔が見えるかで気づかれ度を判断。
- 路面・縁石・白線:濡れ白線・轍・鉄板・マンホールは急制動×。斜めに乗らず直角気味に跨ぐ。
- 合図と意思表示:早めのウインカー(3秒以上)+軽いポジション変更で“行きます”を宣言。
- ドア開き予兆:停車車両のブレーキ解除/車内人影/後席の動きは危険サイン。差速を5〜10km/hに抑制。
- 視線とアイコンタクト:ドライバーがこちらを見た瞬間まで、決定的な進入をしない。
シチュエーション別ベストプラクティス|渋滞列/右折待ち/バス・大型車脇/雨夜
- 渋滞列(0〜10km/h)
- 差速+10〜15km/h以内。クラクション多用は避け、短いハイビームチョイ点灯は“状況で”のみ。
- 先頭30mは信号変化で一斉発進が起こるため無理な前詰め×。
- 右折待ち列の脇
- 相手の対向車確認→急発進があるため、車体前端を越えない位置で様子見。
- 自分が直進なら青でも1テンポ遅れてクリアを確認。
- バス・大型車の脇
- 内輪差・張り出し・吸い込み風。**並走せず“後方→一気に前へ→すぐ離れる”**の一筆書き。
- 右左折のウインカーが出たら接近禁止。
- 雨・夜間
- 差速-5〜10km/h補正。シールド撥水・曇り止めを事前整備。
- リアに反射ベルト、靴やバッグにもリフレクターを追加して360°被視認。
実務のコツ:「迷ったらやめる」「死角にいない」「短時間で抜ける」。この3つを合言葉にすれば、事故・トラブル・違反の確率はまとめて下がります。
ここがNG|「禁止しない」=「いつでもOK」ではない
“全面禁止ではない”からといって、どこでも・いつでも・どんな速度でも良いわけではありません。法規上アウトになりやすい場所・状況と、事故が起きやすい条件を先に押さえましょう。
交差点直前/横断歩道付近/見通しの悪いカーブでのすり抜け
- 交差点直前:右左折車・歩行者・自転車が一斉に動くゾーン。ここでの前詰めや割込みは追越し禁止や進路変更の違反に直結しやすく、接触時は高確率で不利評価。
- 横断歩道付近:歩行者の飛び出しや“見落とし停止車”が典型。差速ゼロ〜超徐行でも通過は避け、先頭から十分な距離を空けて待機が無難。
- 見通し不良カーブ:対向のはみ出し・路面変化・停車車の存在が読みにくい。レーン間の滞在自体が危険。安全余地を確保できないなら見送りが正解。
路肩・すり抜けの取り違え/対向車線の走行は即アウト
- 路肩走行:白線外は通行部分ではないため通行区分違反に該当しやすい。砂利・段差・駐停車車両のドア開きなど、物理的リスクも最大級。
- “側方通過”と“追越し”の混同:前車の直前に割り込む、交差点手前で前に出るなどは追越しの禁止規定に触れる恐れ。
- 対向車線の利用:センターライン越えや対向車線を使った“抜け”は危険運転+違反のセット。視界・制動距離・対向流の不確実性が重なり、事故時の過失も重く見られがち。
騒音・幅寄せ・煽り等のトラブル誘発行為はマナー違反+別件リスク
- 大音量アピールや空ぶかし:周囲の警戒を上げるどころか敵対的反応を生みやすい。地点によっては騒音関連の別件に。
- 幅寄せ・蛇行・急接近:四輪側の驚愕反応→急な進路変更を誘発。危険運転評価や安全運転義務違反の材料に。
- 不要なクラクション連打:法的にも警音器の不適切使用になり得る。合図はウインカー・視線・位置取りで“読める動き”を。
迷ったら“やらない”。先頭30m・横断歩道・白線外・大型車脇は“地雷エリア”だと覚えておきましょう。安全に通れない条件がひとつでも揃ったら、待つ勇気が最適解です。
四輪ドライバー視点の不満と解決策
すり抜けにヒヤッとした経験、ありますよね。四輪側の「驚かされる/怖い」は、**“予測できない動き”と“見えない位置取り”**が原因のほとんど。ここでは、お互いにストレスを減らすための実務的なコツをまとめます。
「驚かされる/怖い」を減らす合図術|位置取り・灯火・クラクションの是非
- 二輪側
- 早めの合図(3秒以上)+一定のラインで「これから通ります」を明確に。
- 差速は控えめ(+15km/h以内が目安)。車内からは距離感が狂って見えるので、近接しすぎない。
- クラクションは緊急回避用途のみ。基本は**位置取りと灯火(デイライト・ポジション)**で存在を“見せる”。
- 四輪側
- ミラー→目視→ゆっくり進路変更の“三段確認”で不意の挟み込みを防止。
- 停車からのドア開放前にミラー&後方確認(同乗者にも声かけ)。
- バイクが近いときは車線中央キープ+急なハンドル操作はしない。
“すり抜けされる側”の守り方|ミラー確認・急なドア開放防止・進路変更の三秒ルール
- ミラー確認の頻度UP:渋滞時・低速時は5〜10秒ごとに後方チェック。
- 進路変更の“三秒ルール”:ウインカー→3秒待って→ゆっくり寄せる。これだけで巻き込み・接触が激減。
- ドア開放対策:停車中でもR(右)→L(左)側の後方確認をルーチン化。ダッチリーチ(反対の手でドアを開け後方を見る)を家族共通ルールに。
- ブレーキの“予告”:渋滞の波に合わせた軽いタッチで早め点灯。バイクに減速意図が伝わりやすい。
共存のためのコミュニケーション設計|譲り/サンキューハザードの適切な使い方
- 譲り合いの見える化:四輪がハンドルを真っ直ぐにして車間を一定に保つだけで、二輪はラインを読みやすい。
- サンキューハザード:二輪側は短い合図1〜2回まで。長点滅は誤解や眩惑の原因に。
- “無理させない距離”:二輪が来たら加速・減速を急に変えない。四輪が譲ってくれたら、二輪は差速を下げて短時間で抜ける。
合言葉は**「予測できる動き」。二輪は早め合図+差速控えめ+短時間通過**、四輪は三段確認+三秒ルール。これだけでヒヤリの大半は消えます。
事故・トラブル時の実務対応
万が一ヒヤリや接触が起きたら、**“安全確保→証拠→通報→保険”**の順で淡々と進めます。感情的な口論は、のちの交渉や過失認定で不利になりがち。ここでは、現場〜事後までの動きを時系列で整理します。
接触時の初動|二次衝突回避→警察→保険→ドラレコ/目撃証言の確保
- 安全確保が最優先:二次衝突を避けるため、可能なら路肩や安全地帯へ退避。発煙筒やハザードで後続に知らせます。
- けが人確認→119/110:軽傷でも頭部・頸部は遅発症状に注意。必ず警察へ届出(事故証明が後で必要)。
- 相手情報の交換:氏名・連絡先・車両番号・保険会社を記録。
- 証拠の確保:
- ドラレコ保存(上書き防止)
- 現場写真(位置関係、ブレーキ痕、信号、標識、路面状況)
- 目撃者の連絡先(可能なら音声で同意録音)
- 保険会社へ連絡:その場で過失割合を断定しない。事実ベースで報告に徹するのがコツ。
ケース別の争点整理|停止車列間すり抜け/走行中並走/ドア開け接触
- 停止車列間すり抜け中の接触:
- 争点は差速・合図の有無・通過位置(レーン間か/同一レーン内か)。
- 先頭直前の割込みは不利材料。**“手前で合図→短時間通過”**が示せる記録が有効。
- 走行中の並走接触:
- 車間・側方間隔と進路変更タイミングが焦点。
- 四輪の**“三秒ルール”の未履行**、二輪の差速過大が指摘されやすい。
- ドア開け(ドアリング)接触:
- 後方安全確認義務の有無が鍵。
- 二輪側は左端走行のライン取り・差速・視認性装備で“予見可能な運転”を立証。
事後に備える装備と記録|前後ドラレコ・GPSログ・ヘルメットカメラ
- 前後2カメのドラレコ:ナンバー読取・夜間性能・広角歪みの少なさを重視。
- GPSログ:走行軌跡と速度変化が差速の妥当性の裏付けに。
- ヘルメットカメラ:視線方向の危険認知や合図のタイミングを示しやすい。
- 保管術:事故時はその日のうちにバックアップ&ファイル名に日時・場所を付与。
実務の合言葉は**「まず安全、次に証拠」**。その場で勝ち負けを決めず、事実を残すことに集中しましょう。
コストと効果|渋滞緩和・環境面・社会的受容
「なぜ全面禁止しないのか?」の背景には、交通効率や社会コストの観点もあります。二輪の占有幅が小さいことは、正しく運用すればスループット(単位時間あたり通過台数)の向上に寄与します。
渋滞時の平均旅行時間短縮の理屈|二輪の占有幅とスループット
- 占有幅が小さい=ボトルネック緩和:渋滞列の**“間”を低速で短時間通過**する二輪が一定割合いると、四輪の再発進・車線変更がスムーズになりやすい。
- ただし条件付き:差速過大・交差点直前の詰め込みは逆効果。波状発進の乱れや合流衝突を招き、全体効率を落とします。
事故コストとのトレードオフ|医療・保険・社会的損失の視点
- 事故は社会的コスト:医療費・休業損失・渋滞悪化が外部不経済として波及。
- “安全策の徹底”が前提条件:差速抑制・視認性強化・禁止区間の遵守で、事故発生確率×損失規模を最小化する設計が必要。
都市設計とインフラ|二輪レーン/ボックスの導入効果(海外事例)
- 二輪待機ボックス(ASL):交差点の先頭停止位置に二輪の待機スペースを設けると、発進時の視認性が上がり、巻き込み事故が低減。
- 二輪レーンの区間導入:バスレーン・自転車レーンの設計配慮とセットで、禁止区間の明確化&期待行動の統一に効果。
- 日本での示唆:まずは**交差点手前30mの“無理な前詰め抑制”**の啓発と、ドラレコ普及で“予見可能な交通”へ。
エッセンスは**「効率のために安全を削らない」**。差速を抑えた短時間通過+禁止区間の厳守が、効率と安全の両立条件です。
よくある質問(FAQ)
「白バイはどう見ている?」現場運用の考え方
- “危険の具体性”を重視:差速、合図、位置取り、禁止区間の遵守など複合的に評価。
- 軽微でも指導あり:ノー合図の割込み/路肩走行/交差点直前の前詰めは、指導・取締り対象になりやすいです。
「原付/大型で違いはある?」車格別の注意点
- 原付:加速・制動余力が小さく、差速の取りすぎが即リスク。10〜15km/h以内を上限目安に。
- 中型〜大型:車幅・熱量・慣性が増えるため、側方間隔のマージンを広めに。短時間通過・死角滞在なしを徹底。
- 共通:ハイビジ装備・前後ドラレコ・早め合図は全クラスで有効。
「ドラレコはどれが良い?」前後2カメ/ナンバー読取/夜間性能の基準
- 必須機能:
- 前後2カメ(広角すぎない画角と歪み補正)
- ナンバー読取性能(昼夜)
- 夜間ノイズ耐性(センサーサイズ・F値・HDR)
- 上書き防止・事故ロック(Gセンサー)
- 運用のコツ:定期的なレンズ清掃/メモリ検証/ファーム更新。事故時は即バックアップ。
迷ったら、**“差速控えめ・早め合図・短時間通過・死角にいない”**の4原則に戻りましょう。結局ここが、安全も法的リスクも最小化する最短ルートです。
関連記事
- 騒音バイクへの仕返し|合法で効く“静かな”対処10選 完全版
- 値落ちしないバイクランキング|手放す時に強いモデルの共通点
- バーエンド ミラー 違法は本当?車検・取り締まりの実情を徹底解説
- バイクのアンダーミラーはダサい?似合う条件とカッコよく見せる技
- バイク リム ステッカー おすすめ|17/18インチ対応・反射/非反射の選び方と貼り方
- バイク ステッカー レトロ完全ガイド|60〜80年代風ロゴの選び方・貼り方
- バイクステッカー ダサい?NG例と即効の改善策|モンスターエナジー問題も解説
- バイク ステッカー おしゃれ|センス良い貼り方・位置・配色の完全ガイド
- バイク用ドラレコは意味ない?付けるべきかを徹底検証【メリット・デメリット】
- バイクのツーリングクラブ うざい理由と上手な付き合い方を解説
- バイク サイドスタンド 傾き調整で転倒防止!初心者でもできる安全対策
- クイックシフターのデメリットとは?コスト・操作性・耐久性の真実
今のバイクを乗り換えたいなら高く売るのが先決!
新しいバイクをお得に手に入れるためには、まず今乗っているバイクをできるだけ高く売ることが重要です。買取額が数万円変わるだけで、次のバイク購入費用や装備のグレードアップに回せる金額が大きく変わります。
特におすすめなのが、「バイクランド」と「バイクワン」の2社です。
バイクランド
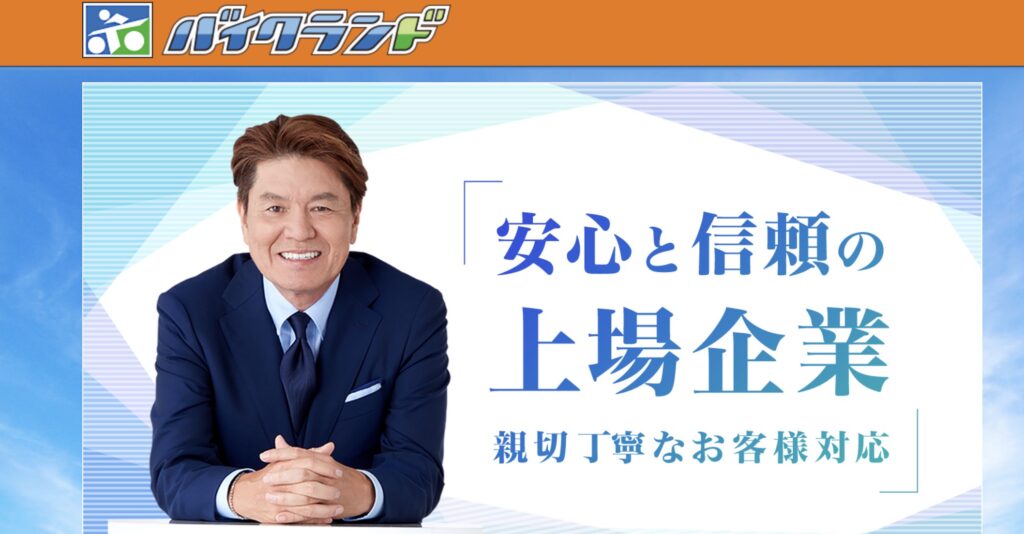
バイクランドは、全国展開する大手バイク買取業者で、年間数万台以上の買取実績を誇ります。安定した査定ノウハウと独自の販売ルートがあり、排気量やジャンルを問わず安定して高額査定を提示してくれるのが強みです。
- 全国対応で出張査定無料
- 大型・旧車・カスタム車でも高値がつきやすい
- 成約後のスピード入金
- 経験豊富な査定士が対応
特に、大型バイクや希少モデルを手放す方には安心感があります。
公式サイトはこちら↓
バイクワン

バイクワンは、バイク買取専門店として全国対応しており、不動車や事故車、ローン残債ありのバイクでも柔軟に対応してくれるのが特徴です。手数料は一切不要で、幅広い車種を高価買取しています。
- 不動車・事故車でも査定OK
- ローン中のバイクも相談可能
- 出張査定・引き取り無料
- 幅広いジャンルのバイクを高価買取
「売れるかどうか不安…」というバイクでも一度相談してみる価値があります。
公式サイトはこちら↓
バイク買取専門店バイクワンまずはこの2社で査定を受けて比較することで、より高い買取額での乗り換えが実現します。
一括査定のように大量の営業電話に悩まされることもないため、安心して利用できます。






